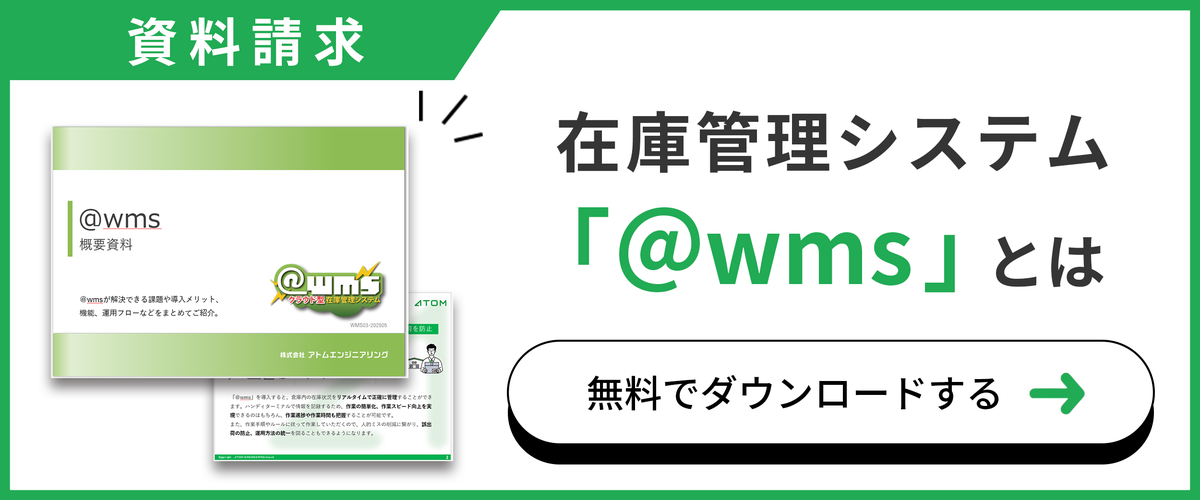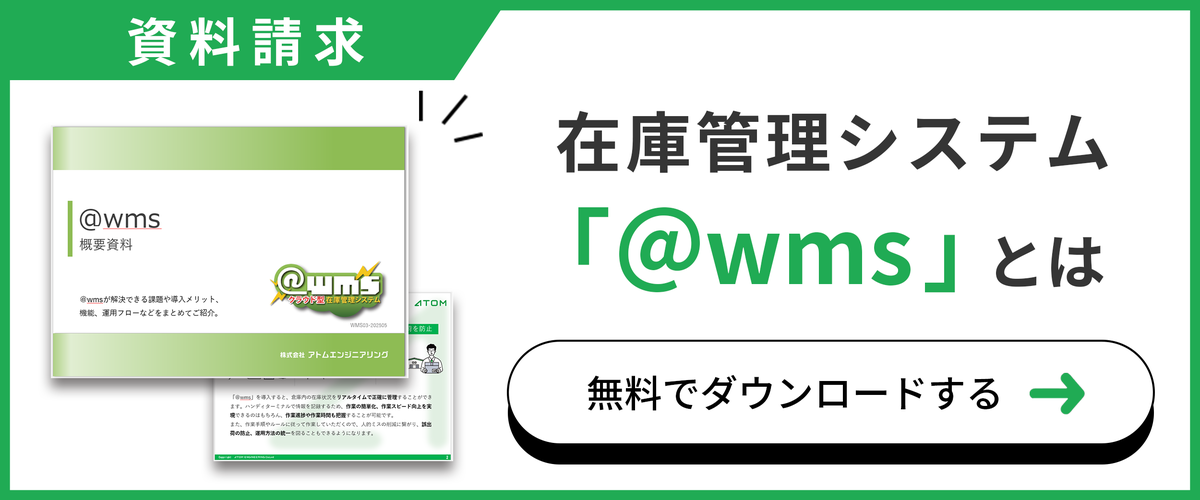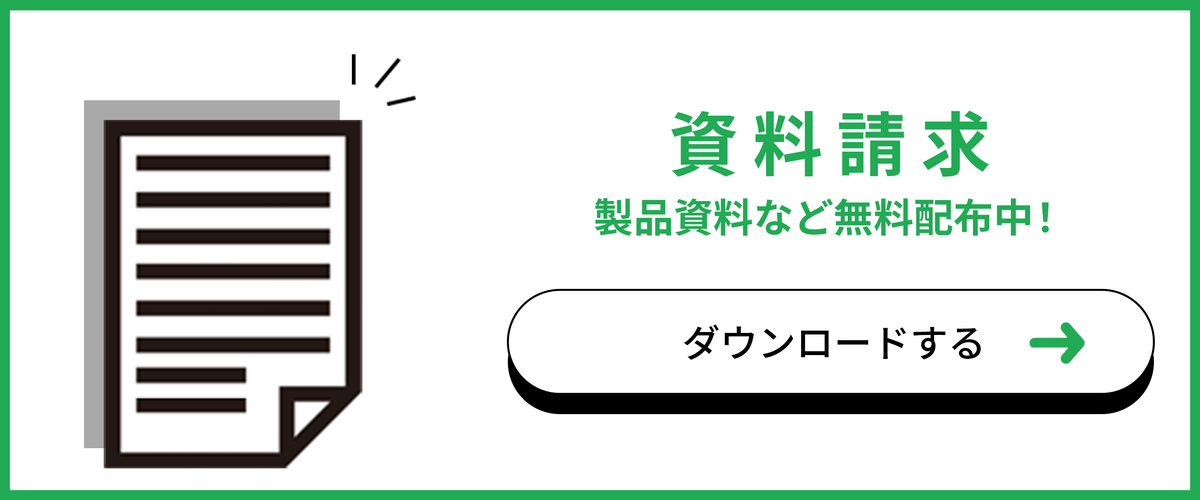お役立ちコラムCOLUMN
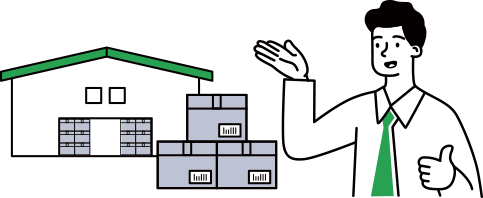
バーコード在庫管理のメリット・デメリットとは?クラウドシステム・アプリ・自作を比較
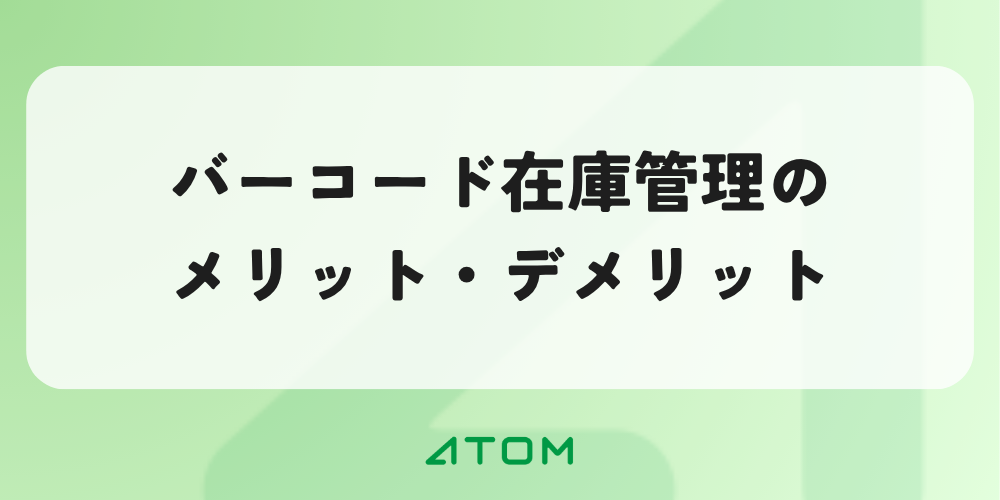
バーコードによる在庫管理は、手作業によるミスを減らし業務効率を大幅に向上させる手法です。
この記事では、バーコード管理の基本的な仕組みから、導入のメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。
さらに、本格的なクラウドシステムの利用、手軽なアプリの活用、Excelでの自作といった導入方法を比較し、自社の状況に合わせた最適な選択ができるよう、それぞれの特徴を明らかにします。
バーコードを使った在庫管理を検討する上で、その利点だけでなく、導入コストや運用面のデメリットも理解することが重要です。
バーコードによる在庫管理とは?
バーコードによる在庫管理とは、商品一つひとつに付与されたバーコードをスキャナーで読み取ることで、在庫の入出庫や保管場所などの情報をデータとして管理する手法です。
このシステムにより、リアルタイムで正確な在庫状況を把握できるようになります。
従来の目視や手入力による管理に比べて、ヒューマンエラーを大幅に削減し、在庫管理業務の効率化と迅速化を実現できるのが特徴です。
特に、多くの品目を扱う倉庫や店舗において、在庫回転率の向上や欠品防止に役立ちます。
「紙やエクセルの管理」と「バーコード・QRコード管理」はどう違う?

紙やエクセルでの在庫管理は、棚札への手書き記帳やPCへの手入力が基本となるため、二度手間や入力ミスが発生しやすいという課題があります。
例えば、倉庫の作業員が棚札に手書きで入出庫を記録し、事務所のオペレーターがその情報をまとめてエクセルに入力するといった二重の作業が発生します。
このプロセスでは、数字の転記ミスや入力漏れが起こりやすく、正確な在庫数の把握を困難にする要因となります。
一方、バーコードやQRコードを使った管理では、ハンディターミナルやタブレットといったモバイルデバイスでコードを読み取るだけで、その場で直接システムへデータが登録されます。
この仕組みにより、モノの動きに合わせてリアルタイムでデータが更新されるため、常に正確な在庫状況を把握できます。
具体的には、入荷時には商品のバーコードを読み取り、出荷時には出荷する商品のバーコードを読み取るだけで、在庫数が自動的に調整されます。
これにより、手作業による入力の手間とミスを大幅に削減し、作業効率と正確性を向上させることが可能です。
また、ロット番号や賞味期限など、より詳細な情報管理が必要な場合は、バーコードよりも多くの情報を格納できるQRコードを活用することで、高度なトレーサビリティ管理も実現できます。
バーコードで在庫管理を行う4つのメリット

バーコード在庫管理を導入することで、さまざまな業務上のメリットが得られます。
在庫状況のリアルタイムな把握から、作業効率の向上、人的ミスの削減、そして業務の属人化防止まで、多角的な視点からその利点を見ていきましょう。
メリット①:在庫状況をリアルタイムで正確に把握できる
バーコードを用いた在庫管理の最大のメリットは、在庫状況をリアルタイムかつ正確に把握できる点です。
入庫や出庫の際にバーコードを読み取ることで、データが即座にシステムへ反映されるため、手作業で発生しがちな記帳漏れやタイムラグがありません。
事務所にいながら現場の最新の在庫数を正確に確認できるため、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による保管コストの増大を防ぐことが可能です。
信頼性の高い在庫データは、需要予測や発注計画の精度を高め、経営判断の質を向上させる基盤となります。
メリット②:入出庫作業の時間を短縮し効率化できる
バーコードをスキャンする作業は、商品名や品番を目で確認し、手書きやキーボードで入力する方法に比べて圧倒的に高速です。
これにより、ピッキングや検品といった入出庫に関わる一連の作業時間が大幅に短縮されます。
作業者は商品を探したり、伝票と照合したりする手間から解放され、より迅速に業務を進めることが可能です。
在庫管理システムと連携することで、入荷から棚入れ、ピッキング、出荷までがスムーズに繋がり、倉庫内業務全体の生産性が向上します。
作業時間の短縮は、人件費の削減にも貢献します。
メリット③:人的ミスを減らし出荷精度が向上する
手作業による在庫管理では、商品の見間違いや数量の数え間違い、伝票への転記ミスといった人的ミスが避けられません。
これらのミスは、誤出荷や在庫差異の原因となり、顧客からの信頼を損なうことにも繋がります。
バーコード管理を導入すれば、スキャナーによる機械的な照合が行われるため、こうしたヒューマンエラーを限りなくゼロに近づけることが可能です。
特に、出荷検品の精度が飛躍的に向上し、正しい商品を正しい数量だけ出荷できる体制が整います。
結果として、返品やクレーム対応にかかるコストや手間も削減できます。
メリット④:誰でも簡単に作業でき属人化を防げる
バーコードをスキャナーで読み取る作業は、直感的で分かりやすく、特別なスキルや長年の経験を必要としません。
そのため、新人や経験の浅い作業者でも短期間で業務を習得でき、即戦力として活躍できます。
作業手順をマニュアルとして作成しやすく、業務の標準化が容易になる点も大きなメリットです。
これにより、特定のベテラン担当者しか在庫状況を把握できないといった属人化の状態を解消します。
担当者の急な欠勤や異動、退職があっても業務が滞るリスクを低減し、安定した倉庫運営を実現します。
バーコード在庫管理を導入する際のデメリット

バーコード在庫管理を導入する際のデメリットとして、主に初期コストの発生、運用ルール策定と従業員教育の必要性、そしてバーコードが読み取れない場合の対応策の検討という3点が挙げられます。
これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることが重要です。
デメリット①:システム導入や機器購入に初期コストがかかる
バーコード在庫管理を始めるには、在庫データを管理するソフトウェアやシステムの導入費用が必要です。
加えて、バーコードを読み取るためのハンディターミナルやバーコードリーダー、ラベルを発行するための専用プリンターといったハードウェアの購入費用も発生します。
特に、管理規模が大きく、高機能なシステムや多数の機器を導入する場合には、初期投資が数百万円単位になることも珍しくありません。
クラウド型のシステムであれば月額利用料、オンプレミス型であれば保守費用といったランニングコストが継続的に発生するため、費用対効果を見極める必要があります。
デメリット②:運用ルールの策定と従業員への教育が必要になる
システムや機器を導入しただけでは、バーコード在庫管理は機能しません。
重要なのは、現場で円滑に運用するためのルールを明確に定めることです。
例えば、どのタイミングでバーコードをスキャンするのか、ラベルが貼られていない商品が入荷した際はどう処理するのか、といった具体的な業務フローをマニュアル化する必要があります。
そして、そのルールを全従業員に周知し、ハンディターミナルやスマホ、タブレットといった新しいデバイスの操作方法を教育しなければなりません。
新しい運用が定着するまでには、一定の時間と労力がかかります。
ただ、そんな時は教育面におけるサポートが手厚い業者を選ぶこともポイントの一つです。
導入後も安心なサポートを受けられるかを事前にチェックしておくと良いでしょう。
デメリット③:バーコードが読み取れない場合の対応策を考える必要がある
バーコードラベル(シール)が汚れたり、印字がかすれたり、破損したりすると、スキャナーで正しく読み取れない場合があります。
また、湾曲した面にラベルを貼った場合や、光の反射によっても読み取りエラーが発生することがあります。
このような事態が発生した際に作業が止まってしまわないよう、あらかじめ対応策を講じておくことが不可欠です。
具体的には、バーコードに併記された数字を手入力する、その場でラベルを再発行して貼り直す、といった代替手段をルールとして定め、作業者全員に周知しておく必要があります。
【目的別】バーコード在庫管理の始め方3選

バーコード在庫管理の導入方法は、企業の規模や予算、求める機能によって様々です。
ここでは、本格的なシステム導入から、スマートフォンアプリの活用、Excelでの自作まで、目的別に3つの導入方法を具体的に解説します。
①本格的な導入なら「在庫管理システム」を利用する
管理する品目数が多く、より高度な在庫管理を目指す企業にとって、専用の在庫管理システムは有力な導入方法の一つです。
在庫管理システムは、リアルタイムでの在庫情報の共有、ハンディターミナルとのスムーズな連携、そして詳細なデータの分析機能など、在庫管理に特化した豊富な機能が備わっています。
特に、複数拠点での在庫管理や、複雑な入出庫処理が求められる場合には、システムが重要な役割を果たします。
近年普及しているクラウド型のシステムは、自社でサーバーを構築・管理する必要がなく、比較的低コストかつ短期間で導入できる点が大きなメリットです。
導入費用は、無料から利用できるものや、初期費用が20~30万円程度で、月額費用が数千円から~数万円程度で利用できるシンプルなシステムから、大規模なシステムでは月額費用が数十万円になるケースもあります。
多くの場合、無料のトライアル期間が設けられているため、実際に操作性や機能性を試した上で、自社に最適なシステムを選定できます。
また、クラウド型システムはインターネット環境があれば場所を選ばずにアクセスできるため、リモートワークや多拠点展開にも対応しやすいという利点があります。
システム選定の際には、既存システムとの連携性や、将来的な拡張性、そしてサポート体制も重要な比較検討ポイントとなります。
②手軽に始めるなら「スマートフォンアプリ」を活用する
小規模な事業者や、まずは手軽にバーコード管理を試してみたいという場合には、スマートフォンアプリの活用が適しています。
手持ちのスマートフォンのカメラをバーコードスキャナーとして利用するため、ハンディターミナルを別途購入する必要がなく、初期費用を抑えることが可能です。
ただし、専用機器と比較すると読み取り速度や精度、耐久性、機能面で見劣りする場合があるため、管理規模の拡大には限界がある点も理解しておく必要があります。
例えば、大量の商品を短時間で読み取る必要がある倉庫業務では、専用のハンディターミナルのほうが効率的です。
また、スマートフォンのバッテリー消費が激しくなることや、屋外での使用に適さないケースも考慮に入れる必要があるでしょう。
そのため、長期的な視点での運用を考えると、将来的な規模拡大を見据えたシステムへの移行も視野に入れることが重要です。
③コストを抑えるなら「Excel」で自作する
ソフトウェアの導入費用をかけずにバーコード管理を始めたい場合、Excelでシステムを自作するという選択肢もあります。
バーコードフォントをインストールし、VBA(マクロ)を用いて入出庫を記録する仕組みを構築する方法です。
この方法はコストを最小限に抑えられる点が最大のメリットですが、作成にはVBAに関する専門知識が不可欠です。
また、複数人での同時編集には向かず、データ量が増えると動作が著しく遅くなるなどのデメリットも多く、あくまで管理品目数が非常に少ない場合の簡易的な手段と考えるべきです。
Excelで管理する場合の注意点
Excelでの自作は、専門知識を持つ担当者に業務が属人化しやすいという大きなリスクを抱えています。
作成者が異動や退職をしてしまうと、不具合が発生した際に誰も修正できず、管理業務そのものが破綻しかねません。
また、Excelファイルは複数人での同時編集を前提としていないため、入力の競合によるデータの上書きや破損が起こりやすいです。
データ量が増加するにつれてファイルの動作が重くなり、実用性が低下することも避けられません。
こうした理由から、事業の継続性や拡張性を考慮すると、本格的な在庫管理の基盤としてExcelを使い続けることは推奨されません。
バーコード在庫管理の導入に必要なもの

バーコード在庫管理を運用するには、情報を読み取る「スキャナー」、商品に貼る「バーコードラベルを発行するプリンター」、データを集約する「システムやソフトウェア」の3つが必要不可欠です。
これらが連携することで、現物の在庫とデータが一致し、正確かつ効率的な在庫管理の仕組みが構築されます。
バーコードを読み取るスキャナー(ハンディターミナルやスマホ)
バーコードを読み取るためのデバイスは、在庫管理の現場における中心的なツールです。
主な選択肢としては、倉庫などの過酷な環境でも使用できる高い耐久性と読み取り性能を持つ業務用の「ハンディターミナル」があります。
一方、導入コストを抑えたい場合は、手持ちの「スマートフォン」に専用アプリをインストールしてスキャナーとして利用することも可能です。
ハンディターミナルは操作性やバッテリー性能に優れますが、スマートフォンに比べると高価です。
ただしスマートフォンは手軽ですが、性能面では専用機に劣る場合があります。 作業環境や予算に応じて選択します。
バーコードラベルを発行するプリンター
管理対象の商品にバーコードが付いていない場合、自社でバーコードラベルを作成し、貼り付ける必要があります。
このラベルを作成するために専用のラベルプリンターが用いられます。
一般的なオフィス用プリンターでも印刷は可能ですが、滲みやかすれが発生しやすく、読み取り精度が低下する恐れがあります。
ラベルプリンターは、耐久性の高いラベルを鮮明に印刷でき、熱で印字するサーマル方式やインクリボンを用いる熱転写方式などがあります。
特に長期間の保管が想定される場合は、印字が消えにくい熱転写方式が適しています。
在庫データを一元管理するシステムやソフトウェア
スキャナーで読み取った在庫情報は、在庫管理の司令塔となるシステムやソフトウェアに集約されます。
このシステムにより、物理的な在庫の動きとデジタルデータが連携し、正確な在庫情報を把握できます。
選択肢は幅広く、在庫管理に特化した単体のシステムから、販売管理、購買管理、会計機能まで統合されたERP(統合基幹業務システム)まで多岐にわたります。
近年では、インターネット経由で利用できるクラウド型のサービスが主流です。
クラウド型は、自社でサーバーを構築・管理する手間がなく、初期費用を抑えやすいのが特徴です。
インターネット環境があれば場所を問わずにリアルタイムで在庫データにアクセスできるため、複数の倉庫や店舗を持つ企業、あるいはリモートワーク環境でも円滑な在庫管理が可能です。
システムを選定する際は、自社の業務フローや既存システムとの連携性を十分に考慮することが重要です。
例えば、既に利用している販売管理システムや会計システムとシームレスに連携できるか、あるいは将来的な事業拡大を見据えた拡張性があるかといった点を検討しましょう。
また、システムの操作性やサポート体制も確認し、現場の従業員がスムーズに利用できる最適なソフトウェアを選ぶことが成功の鍵となります。
導入前に無料トライアルを活用し、実際に利用してみることで、自社に最適なシステムを見つけられるでしょう。
バーコード在庫管理システムの導入手順4ステップ
バーコード在庫管理システムを効果的に導入するためには、計画的なアプローチが不可欠です。
やみくもにシステムを導入しても、現場の混乱を招くだけで期待した効果は得られません。
まずは現状の課題を正確に把握することから始め、その課題を解決できる最適なシステムを選定します。
その後、具体的な運用ルールを定めて準備を進め、最終的にテスト運用を経て本格導入へと移行する、という4つのステップを踏むことで、導入の失敗リスクを大幅に低減させることが可能です。
STEP1:現状の在庫管理における課題を洗い出す
導入成功の第一歩は、現在の在庫管理方法が抱える問題点を具体的に洗い出すことです。
「なぜ在庫数が合わないのか」「どの作業に時間がかかっているのか」「誤出荷はどのような状況で発生しているのか」など、現場で起きている問題を具体的にリストアップします。
例えば、「手書き伝票の転記ミスが多い」「棚卸しに数日かかっている」「ベテラン社員しか商品の場所が分からない」といった課題を可視化することで、システム導入によって何を達成したいのかという目的が明確になります。
この目的が、後のシステム選定における判断基準となります。
STEP2:自社の課題を解決できるシステムや機器を選定する
洗い出した課題を基に、それを解決する機能を備えたシステムや機器を選定します。
例えば、「リアルタイムな在庫共有」が課題であればクラウド型のシステム、「ピッキング作業の高速化」が目的なら読み取り性能の高いハンディターミナル、といったように、課題と解決策を具体的に結びつけて検討します。
複数の販売業者から資料を取り寄せたり、デモンストレーションを依頼したりして、機能、コスト、操作性、サポート体制を比較評価します。
この際、無料トライアルなどを活用し、実際に現場の担当者が使いやすいかどうかを確認することが極めて重要です。
STEP3:商品にバーコードを付与し、運用ルールを明確にする
導入するシステムと機器が決まったら、本格稼働に向けた準備を進めます。
管理対象となるすべての在庫品にバーコードを付与する作業が必要です。
商品にJANコードなど既存のバーコードがあればそれを活用し、ない場合は自社で管理用のバーコードを採番してラベルを作成・貼付します。
並行して、新しい業務フローに合わせた運用ルールを具体的に定めます。
入庫、出庫、棚卸し、返品処理など、各業務プロセスにおいて「誰が、いつ、どのタイミングで、どのデバイスを使ってスキャンするのか」を詳細にマニュアル化し、現場の混乱を防ぎます。
STEP4:テスト運用を開始し、本格導入へ移行する
準備が整ったら、全社で一斉に本稼働させるのではなく、まずは特定の部署や商品カテゴリに限定してテスト運用を行うことが重要です。
このスモールスタートによって、策定した運用ルールに無理がないか、システムに予期せぬ不具合はないか、作業者がスムーズに操作できるかなどを実践的に検証できます。
テスト運用中に発見された問題点や改善点をフィードバックし、ルールや設定を修正します。
このプロセスを経て、運用の確実性を高めた上で、対象範囲を段階的に広げて本格導入へと移行することで、スムーズな定着が実現します。
バーコードの在庫管理に関するよくある質問
バーコード在庫管理は、業務の正確性と効率性を向上させる有効な手段であり、導入を検討する際には多くの疑問が生じることでしょう。
ここでは、よく寄せられる質問について詳しく解説していきます。
Q. バーコードが付いていない商品も管理できますか?
はい、管理できます。
市販品のようにJANコードが付いていない商品でも、在庫管理システムを使って商品ごとにユニークな管理番号を割り当て、その番号に基づいたバーコードを生成することが可能です。
生成したバーコードは、ラベルプリンターでシールとして出力し、商品そのものや、商品を保管している棚、コンテナなどに貼り付けます。
このプロセスを経ることで、自社で製造した部品や製品、仕入れた原材料など、あらゆる在庫品をバーコードで一元管理できるようになります。
これにより、管理対象を限定することなく、全ての在庫を同じ仕組みで管理できます。
Q. 導入にかかる費用の目安はどれくらいですか?
導入費用は、選択するシステムや機器、管理規模によって大きく異なります。
最も手軽なスマートフォンアプリの場合、月額数千円から数万円程度で利用できるサービスが多く、初期費用はほとんどかかりません。
一方、本格的なクラウド型在庫管理システムを導入し、専用のハンディターミナルやラベルプリンターを複数台購入する場合、初期費用として数十万円から、規模によっては数百万円以上が必要になることもあります。
加えて、システムの月額利用料や保守費用といったランニングコストも発生するため、複数の提供会社から見積もりを取得し、比較検討することが不可欠です。
Q. QRコードでの在庫管理との違いは何ですか?
バーコードとQRコードの最も大きな違いは、記録できる情報の量です。
バーコードが一次元(横方向)にしか情報を持たず、記録できる桁数はある程度限られています。
これに対し、QRコードは二次元(縦横)に情報を持ち、数字であれば最大で7,089文字という、バーコードの数百倍もの情報を格納できます。
この情報量の差を活かし、QRコードでは商品コードに加えて、ロット番号や製造年月日、賞味期限、シリアル番号といった複数の属性情報を一つのコードに含めることが可能です。
そのため、トレーサビリティや品質管理が重要な業界で広く採用されています。
まとめ
バーコードによる在庫管理は、紙やExcelでの手作業管理が抱える課題を解決し、業務の正確性と効率性を飛躍的に向上させる有効な手段です。
在庫状況のリアルタイムな可視化、入出庫作業の迅速化、人的ミスの削減、業務の標準化といった多くのメリットをもたらします。
一方で、導入には初期コストや運用ルールの策定といった準備も必要です。 本格的な在庫管理システムから手軽なスマートフォンアプリ、Excelでの自作まで、導入方法には複数の選択肢があります。
まずは自社の現状の課題を明確にし、事業規模や目的に合った方法を選択することが、導入を成功させる第一歩となります。
本格的なシステム導入ならクラウド在庫管理「@wms」
倉庫の在庫管理をバーコードでお考えなら、クラウド在庫管理「@wms」をご検討ください。
@wmsは、バーコード読み取りをスマートフォン・ハンディターミナルで利用でき、外出先からでもリアルタイムの在庫確認など、エクセルでは不可能な機能が実現できます。
月額固定料金のクラウドシステムで、利用環境・デバイス数に応じた導入費用となっているため、ご予算に合わせたご提案が可能です。
バーコード在庫管理をご検討の方は、まずはアトムエンジニアリングまでお気軽にご相談ください。