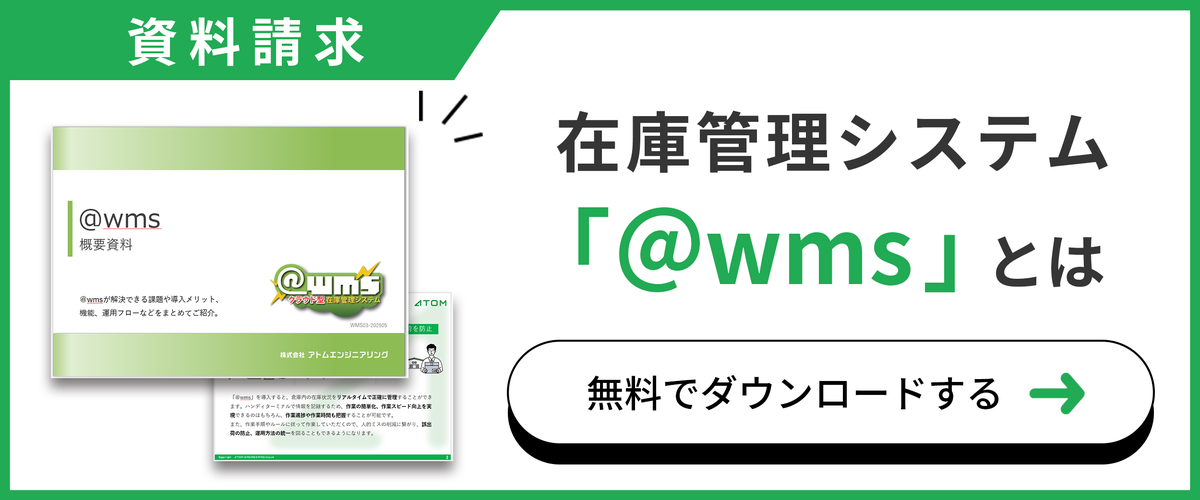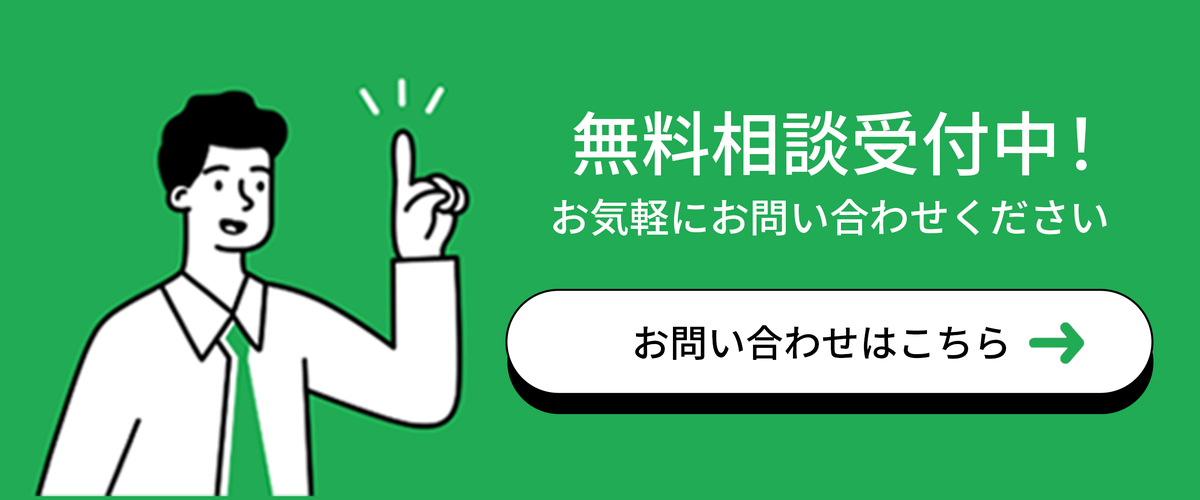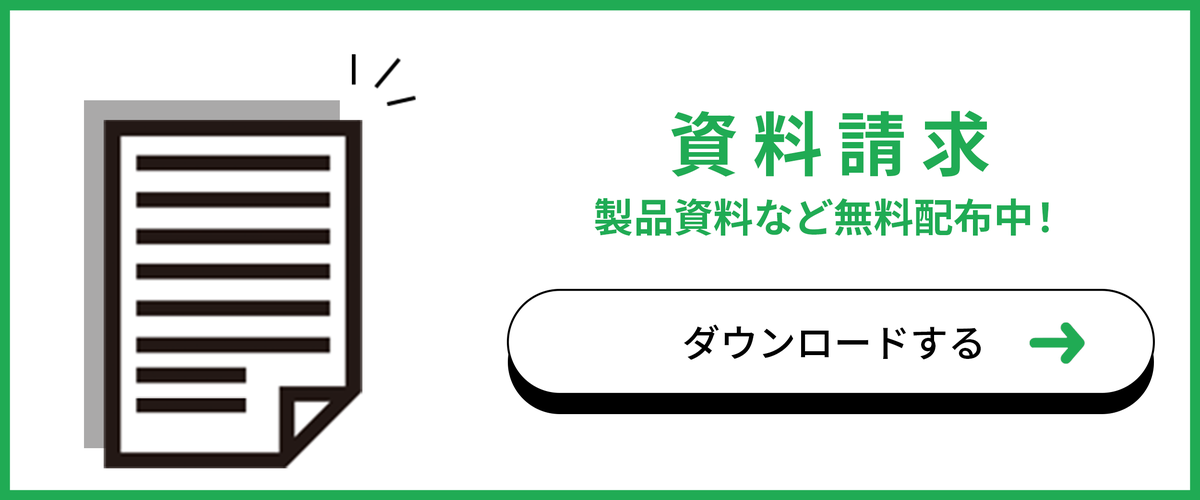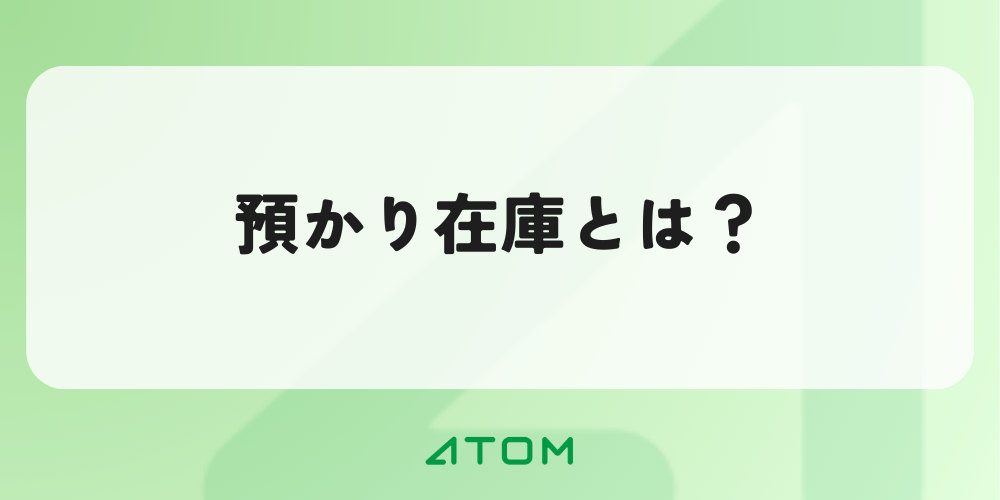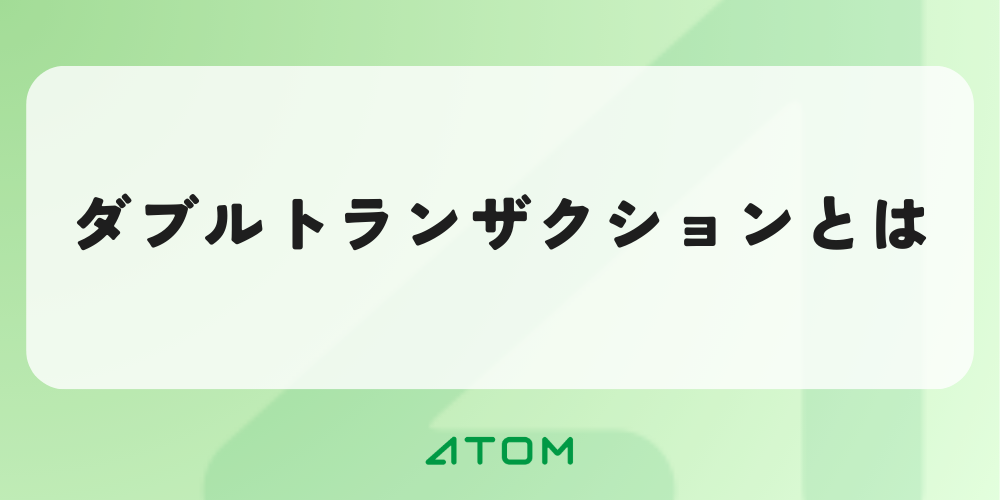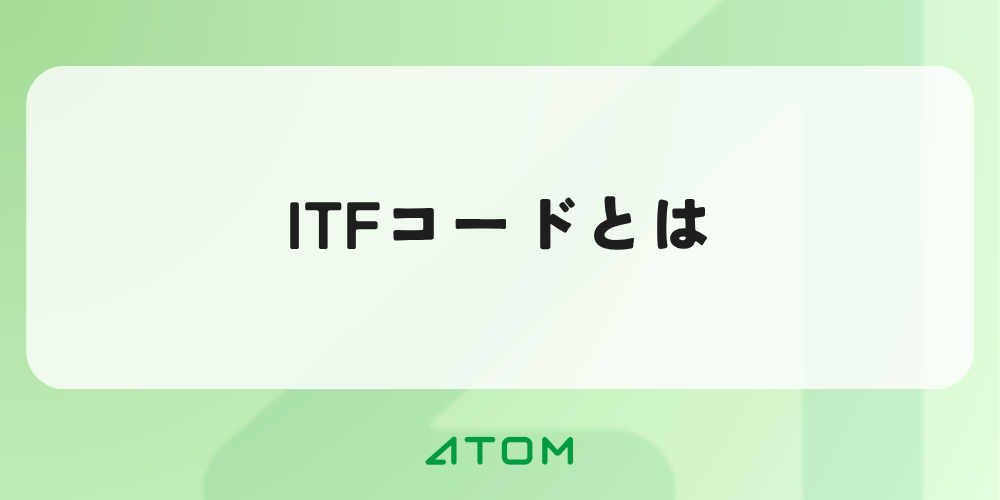お役立ちコラムCOLUMN
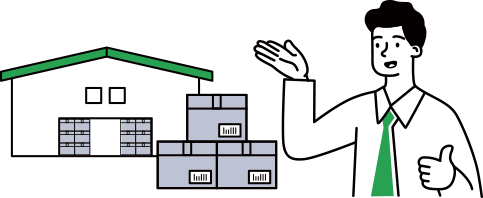
固定ロケーションとは?具体例付きでフリーロケーションとの違いやメリットを解説
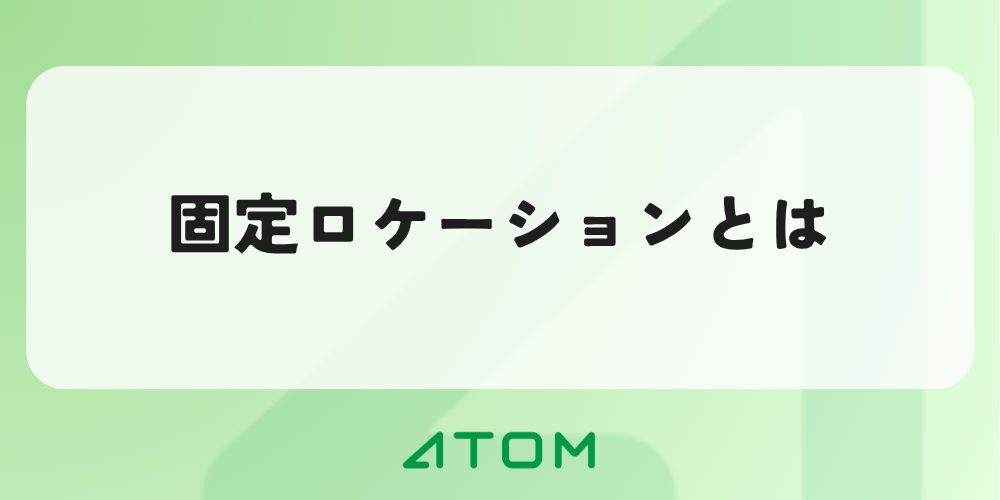
固定ロケーションとは、倉庫内で商品の保管場所を品目ごとにあらかじめ決めておく在庫管理方法です。
対照的なフリーロケーションとの違いを理解し、それぞれのメリットを把握することが重要となります。
例えば、作業の習熟しやすさや管理の簡便さなど、固定ロケーションには多くの利点が存在します。
この記事では、固定ロケーションの基本から、導入のメリット・デメリット、運用を効率化する具体的なポイントまで、分かりやすく解説します。
固定ロケーションとは?商品の保管場所をあらかじめ決める管理方法

固定ロケーション方式とは、倉庫内において、特定の商品を保管する場所をあらかじめ固定する在庫管理手法です。
この方式では、商品と保管場所が1対1で紐づけられます。
そのため、作業者は商品の場所を覚えやすく、ピッキングリストに記載された商品を探す際に迷うことが少なくなります。
経験の浅い作業者でも場所を特定しやすいため、作業品質の標準化に繋がり、効率的な入出庫作業を実現します。
例えば、特定の商品が常に「A棟1列3棚」といった具体的な住所を持つことで、新人作業員でも迷うことなく目的の商品にたどり着くことが可能です。
このような固定ロケーション方式は、特に商品の種類が限定的で、比較的変動が少ない倉庫において、高い効果を発揮します。
固定ロケーションとフリーロケーションの3つの違いを比較
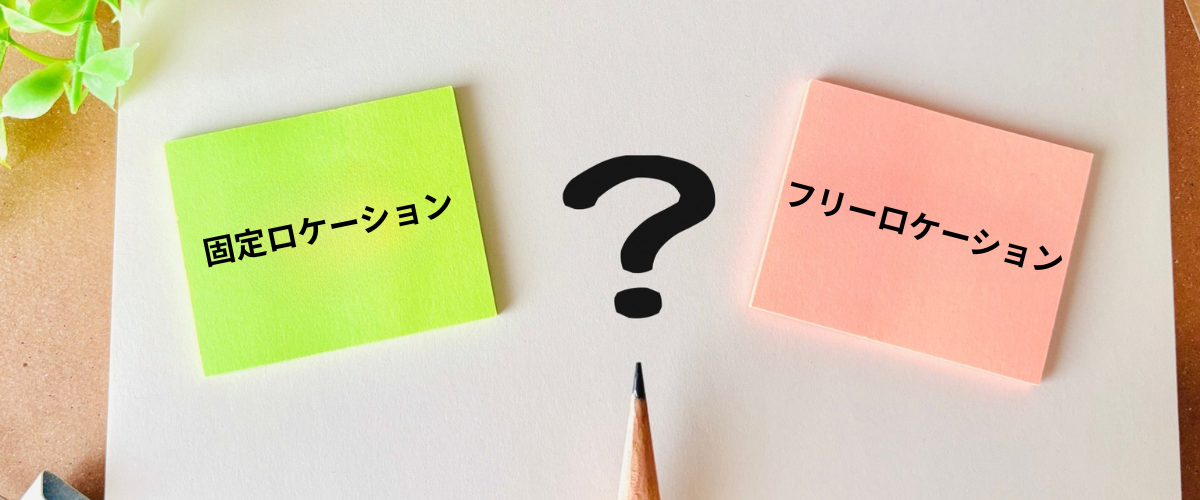
固定ロケーションと対比される管理方法に、フリーロケーションがあります。
フリーロケーションは、商品を保管する場所を固定せず、入庫時に空いているスペースに格納していく手法です。
これら2つの方法は、保管場所の考え方、作業の習熟度、スペース効率の面で大きな違いがあります。
どちらの方式が自社の倉庫に適しているかを判断するためには、それぞれの特性を正しく理解し、比較検討することが不可欠です。
違い①:商品の保管場所が固定か空きスペースか
最も基本的な違いは、商品の保管場所に関する考え方です。
固定ロケーションでは、商品ごとに「住所」が割り当てられ、常に同じ場所に保管されます。
例えば、Aという商品は常に「1階A通路3番棚」に置かれるため、どこに何があるかが一目瞭然です。
これは、図書館で書籍が分類番号に基づいて決まった棚に置かれるのと似ています。
一方、フリーロケーションでは、倉庫管理システム(WMS)でその都度任意のロケーションを指定でき、そこに商品を保管します。
そのため、Aという商品が昨日と今日で全く違う場所に保管されることも珍しくありません。
この方式は、どこに何があるかを人が記憶するのではなく、WMSによるロケーション管理が前提となります。
・「倉庫管理システム(WMS)とは・・・
フリーロケーションを導入することで、倉庫内のデッドスペースを減らし、保管効率を高められます。
例えば、スーパーマーケットのバックヤードで、その日入荷した商品を空いている棚に順次補充していくイメージです。
どちらの方式を選択するかは、扱う商品の種類や数量、倉庫の規模、導入するシステムの有無によって検討する必要があるでしょう。
違い②:作業の習熟のしやすさ
作業の習熟のしやすさという点では、固定ロケーション方式に軍配が上がります。
商品の保管場所が常に同じであるため、作業者は日々の業務を通じて自然と商品の配置を記憶できます。
例えば、新人作業員であっても、ロケーションマップがあれば迷うことなく目的の場所に到達できますし、経験を積めばピッキングリストを見るだけで倉庫内の最短ルートを思い描き、効率的に作業を進めることが可能です。
これにより、作業スピードが向上し、全体の生産性向上に貢献します。
対してフリーロケーションは、毎回システムが指定する場所へ向かう必要があるため、作業者の経験や勘が活きにくく、習熟による作業スピードの向上には限界があります。
システムからの指示に常に従う必要があるため、作業員が自らの判断で効率的なルートを選択する機会が少ない点が特徴です。
したがって、作業の属人化を防ぎ、標準化された作業を求める場合は固定ロケーション方式が有利と言えるでしょう。
違い③:倉庫スペースの利用効率
倉庫の保管スペースをどれだけ有効に使えるかという利用効率の観点では、フリーロケーションが優れています。
固定ロケーションは、特定商品の在庫が少なくなったり、一時的に欠品したりしても、その商品のために確保されたスペースを他の商品で埋めることはできません。
例えば、100個の商品を保管するために確保された棚に、現在50個しか在庫がない場合、残りの50個分のスペースは空いたままとなり、他の商品の保管には利用できないのです。
これにより、倉庫内に空きスペース(デッドスペース)が生まれやすくなります。
一方、フリーロケーションは空いている棚から順に商品を格納していくため、スペースの無駄が少なく、保管効率を最大限に高めることが可能です。
空いているスペースを無駄なく活用できるため、倉庫全体の保管能力を向上させられます。
特に、扱う商品点数が多く、季節によって在庫の変動が激しいアパレル製品や、頻繁に新商品が追加される日用雑貨などを扱う場合に、この差は顕著に現れ、フリーロケーションの利点が際立ちます。
固定ロケーションを導入する3つのメリット

固定ロケーションの導入は、倉庫業務において多くの利点をもたらします。
特に、作業の効率化、在庫管理の正確性向上、そして導入のしやすさは大きなメリットと言えるでしょう。
これらのメリットは、作業者の負担軽減や教育コストの削減、さらには顧客サービスの向上にも間接的に貢献します。
ここでは、固定ロケーションがもたらす3つの主要なメリットについて、具体的な内容を掘り下げていきます。
メリット①:作業者が商品の場所を覚えやすくピッキングが速い
固定ロケーションがもたらす最大のメリットは、ピッキング作業のスピード向上です。
商品の保管場所が常に決まっているため、作業者は「どの商品がどこにあるか」を身体で覚えることができます。
特に、長年勤務している熟練作業者は、広大な倉庫内でも迷うことなく、最短経路で複数の商品を効率的に集めることが可能です。
新人作業者でも、ロケーション番号が振られた棚とリストを照合すればよいため、比較的早く作業に慣れることができます。
この作業の属人化を防ぎつつ、全体の生産性を高められる点が、大きな強みとなります。
また、商品の保管場所が明確であることは、新人教育のコスト削減にも繋がるメリットもあります。
例えば、食品倉庫で賞味期限が近い商品や人気のある商品が決まった場所に保管されていれば、経験の浅い作業者でも迷わず迅速に取り出せるため、誤出荷のリスクを低減させ、顧客満足度の向上にも貢献します。
メリット②:どこに何があるか明確で在庫管理がしやすい
どこに何があるかが明確であるため、在庫管理が非常にしやすい点もこのメリットの1つです。
各商品の定位置が決まっていることで、目視による在庫確認や棚卸作業がスムーズに進みます。
例えば、特定の商品が常に同じ棚にあるため、棚卸し時には該当棚を確認するだけで済み、効率が向上します。
また、あるべき場所に商品がなければ、それは欠品や紛失、あるいは別の場所に誤って置かれているといった異常事態であるとすぐに判断できます。
これにより、例えば、ある棚が空になっている場合、システムで確認する前に「商品がない」と判断でき、迅速な対応が可能です。
このように、在庫状況の可視性が高まることで、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫のリスクを低減させ、より正確な在庫管理を実現します。
この管理の明瞭さは、誤出荷の防止にも繋がります。
メリット③:高価な管理システムがなくても運用を始められる
導入ハードルの低さも、固定ロケーションの大きなメリットの一つです。
フリーロケーションが倉庫管理システム(WMS)の導入をほぼ必須とするのに対し、固定ロケーションは比較的シンプルな仕組みで運用を開始できます。
例えば、Excelでロケーション管理表を作成し、各棚に番号を振るといった手作業ベースの管理も可能です。
これにより、高価なシステムを導入しなくても、在庫管理をスタートできる点が大きな利点となります。
そのため、大規模な初期投資を行うことが難しい中小企業や、まずはスモールスタートで倉庫管理を始めたいという場合にも適しています。
この手軽さは、特に初めて倉庫管理の最適化に取り組む企業にとって、導入への心理的障壁を大きく下げるでしょう。
もちろん、WMSを導入し固定ロケーション方式を採用するのも効果的です。
その場合は、商品の種類数や在庫の変動性を考慮し検討するのが良いでしょう。
知っておきたい固定ロケーションの2つのデメリット

固定ロケーションは多くのメリットを持つ一方で、いくつかのデメリットも存在します。
導入を検討する際には、これらの課題を事前に理解し、自社の状況と照らし合わせて対策を講じることが重要です。
特に、スペース効率の問題と、定期的なメンテナンスの必要性は、運用コストや作業効率に直接影響を与える可能性があります。
ここでは、知っておくべき2つのデメリットを具体的に解説します。
デメリット①:保管スペースに空きが生まれやすく非効率になることがある
固定ロケーションにおける最も顕著なデメリットは、保管スペースの利用効率が低下しやすい点です。
各商品に専用の保管場所を割り当てるため、ある商品の在庫が少なくなったり、季節性の問題で一時的に在庫がゼロになったりした場合、そのスペースは空いたままになります。
この空きスペース(デッドスペース)を他の商品で埋めることができないため、倉庫全体の保管効率が悪化する可能性があります。
限られた倉庫スペースを最大限に活用して多くの商品を保管したい場合には、このデメリットが大きな課題となり得ます。
デメリット②:商品の入れ替えに合わせて定期的な棚の見直しが必要になる
もう一つのデメリットとして挙げられるのが、固定ロケーションを最適な状態で維持するためには、定期的な見直し、すなわちロケーションメンテナンスが不可欠である点です。
市場の動向によって売れ筋商品は常に変化するため、かつて頻繁に出荷されていた商品が出荷されなくなった場合、出荷口近くの一等地に配置し続けるのは非効率的です。
例えば、季節限定商品やキャンペーン商品などは、その時期が過ぎれば出荷頻度が大幅に減少します。
そうした商品を最優先の場所に置き続けることは、他の高頻度出荷商品のピッキング効率を低下させるデメリットにつながる可能性があります。
また、新商品の追加や終売品の発生に合わせて、棚の割り当ても変更しなければなりません。
このような見直し作業を怠ると、作業員の移動距離が長くなるなど、固定ロケーションのメリットである作業効率の高さが損なわれてしまいます。
継続的な管理の手間は発生しますが、このメンテナンスを適切に行うことで、常に効率的なロケーションを維持し、メリットを最大化することが可能となります。
固定ロケーションの運用効率を上げる3つのポイント

固定ロケーション方式を導入しても、運用方法が適切でなければメリットを最大限に活かすことはできません。
デメリットを抑制し、効率的な倉庫運営を実現するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ここでは、分かりやすいロケーション番号の付与、ABC分析を活用した最適な商品配置、WMS導入による管理の自動化という、運用効率を飛躍的に向上させる3つのポイントについて解説します。
ポイント①:誰でもわかるようにロケーション番号を付ける
固定ロケーション方式の基本は、誰が見ても場所を特定できる、分かりやすいロケーション番号を付与することです。
例えば、「A-01-02-3」のように、「エリア-列-連-段」といった階層構造でルールを統一すると、作業者は住所を頼りに目的地を探すように、直感的に場所を把握できます。
この番号を棚や床に明示し、倉庫全体のマップを作成しておくことで、新人作業員でもピッキングリストの指示だけで迷わずに作業を進めることが可能になります。
これにより、教育にかかる時間を短縮し、ピッキングミスを削減する効果も期待できます。
特に、固定ロケーション方式は、商品の種類が多く、作業員の入れ替わりが頻繁な倉庫において、作業品質の標準化に貢献し、生産性向上に繋がる重要な要素となります。
ポイント②:ABC分析で出荷頻度の高い商品を最適な場所に配置する
固定ロケーション方式の効率をさらに高めるためには、商品の配置が極めて重要です。
そこで有効な手法がABC分析です。
全商品を売上や出荷頻度などに基づいて重要度別にA・B・Cの3グループに分類します。
具体的には、出荷実績データや売上データを基に、各商品の重要度を数値化してランク付けを行います。
例えば、上位20%の商品で売上の80%を占める場合、その20%がAグループに該当するといった形で分類します。
そして、最も出荷頻度の高いAグループの商品を、出荷口に最も近く、作業者の目線の高さなど取り出しやすいゴールデンゾーンに配置します。
これにより、ピッキング作業における移動距離を大幅に短縮でき、作業時間の削減に直結します。
逆に、出荷頻度の低いCグループの商品は、倉庫の奥や棚の上下段といった、アクセス頻度の低い場所に配置します。
この最適な配置により、作業者の移動距離と時間を最小限に抑え、ピッキング作業全体の生産性を向上させることができます。
また、定期的なABC分析の見直しを行うことで、商品の出荷頻度の変化に対応し、常に最適なロケーションを維持することが、固定ロケーション方式を最大限に活用する上で重要です。
ポイント③:WMS(倉庫管理システム)を導入して管理を自動化する
固定ロケーション方式は手作業での運用も可能ですが、WMS(倉庫管理システム)を導入することで、管理を自動化し、さらなる効率化と精度向上が実現できます。
WMSを活用すれば、在庫情報をリアルタイムで更新し、入出庫作業をデジタルで一元管理することが可能です。
これにより、手作業による入力ミスや棚卸し作業の負荷が大幅に軽減され、ヒューマンエラーの削減と管理工数の圧縮に繋がります。
例えば、特定の商品の在庫数が減った際に自動で発注を促したり、入庫された商品を最適なロケーションに案内したりと、システムが倉庫業務全体をサポートします。
WMSには、ABC分析の結果に基づいて最適な保管場所を提案する機能や、複数の注文をまとめて最も効率的なピッキングルートを指示する機能など、高度な在庫管理を支援する機能が豊富に搭載されています。
特にSKU数(「Stock Keeping Unit」(在庫管理単位)の略で、在庫管理における最小の品目単位を指します。 )が多い倉庫や、より高度な在庫管理を目指す企業にとって、WMSの導入は、効率的で正確な倉庫運営を実現するための有効な選択肢となるでしょう。
自動化された管理によって、作業者はピッキングや梱包といった付加価値の高い業務に集中できるようになり、全体の生産性向上にも貢献します。
固定ロケーションの導入がおすすめなケース

固定ロケーションは、特定の条件下でその真価を発揮し、倉庫運営に大きな効果をもたらします。
主に、取り扱う商品の種類が少なく、かつ定番品を安定して供給する業態において特に有効です。
具体的には、商品の入れ替わりが頻繁でなく、長期間にわたって同じ商品を扱う倉庫に適しています。
例えば、特定メーカーの工業製品や機械部品、あるいは特定のブランドに絞られたアパレル商品などを扱う倉庫では、固定ロケーションの導入により、効率的な在庫管理が期待できます。
また、商品のサイズや形状がある程度均一で、保管に必要なスペースを予測しやすい場合も、固定ロケーションのメリットを享受しやすいです。
これにより、デッドスペースの発生を最小限に抑えつつ、効率的な倉庫運用が可能となります。
さらに、作業の標準化と効率化を図りたいと考える企業にとって、固定ロケーションは有力な選択肢となるでしょう。
特に、人による作業習熟度を重視し、作業員の入れ替わりが少ない企業や、シンプルな管理体制を維持したい企業におすすめです。
まとめ
この記事では、固定ロケーションとは何か、その基本的な概念から、フリーロケーションとの違い、そして導入におけるメリット・デメリットまでを解説しました。
固定ロケーションは、商品ごとに保管場所を固定することで、作業者が場所を覚えやすくピッキング効率が高いというメリットを持つ一方、保管スペースに無駄が生じやすいというデメリットも抱えています。
自社の倉庫にこの方式が適しているかを見極めるには、取り扱う商品の種類、在庫の変動性、作業者の習熟度などを総合的に考慮する必要があります。
その上で、ABC分析による配置の最適化やWMSの活用といった工夫を取り入れ、メリットを最大化させることが倉庫運営の効率化に繋がります。