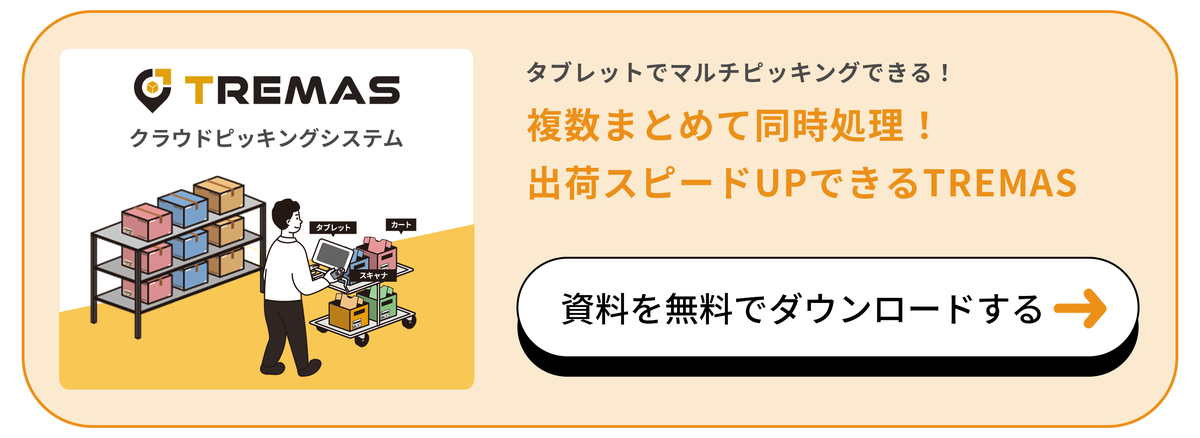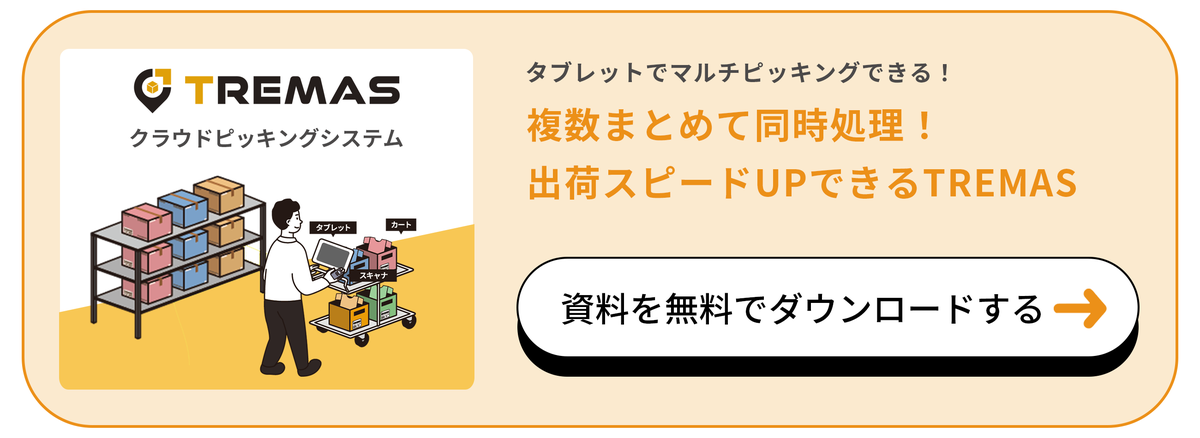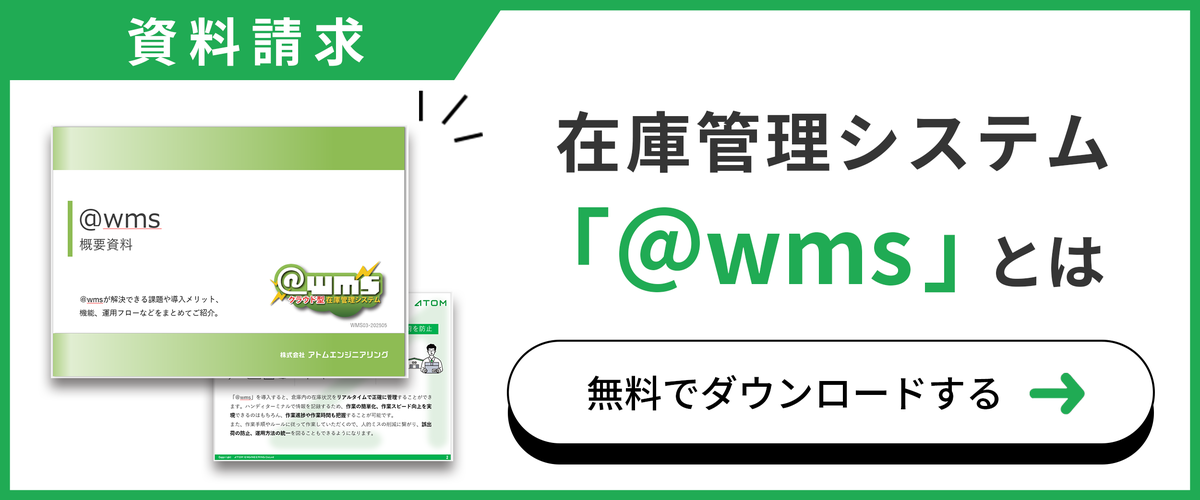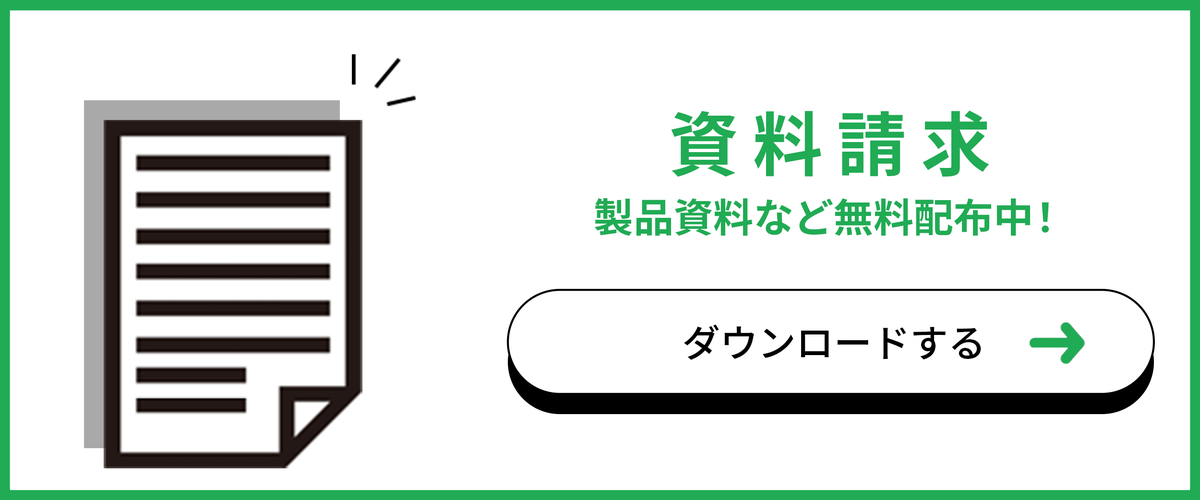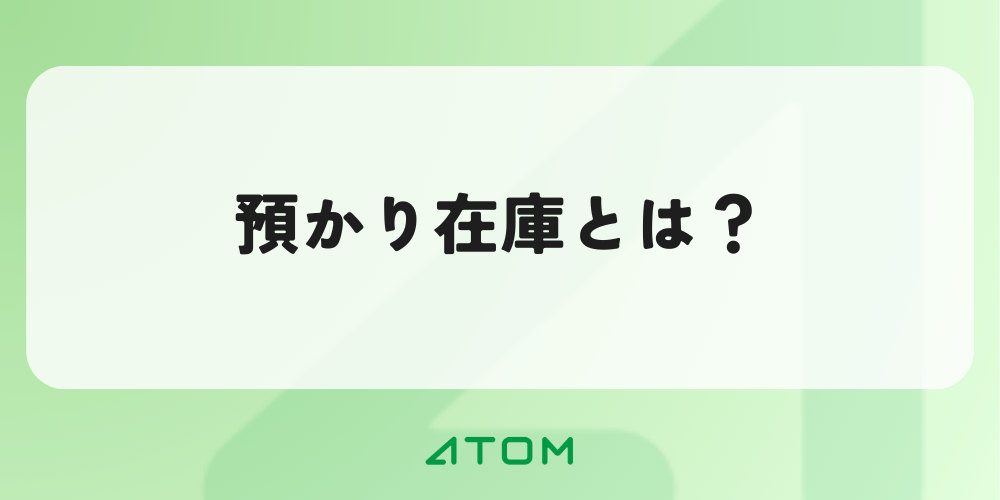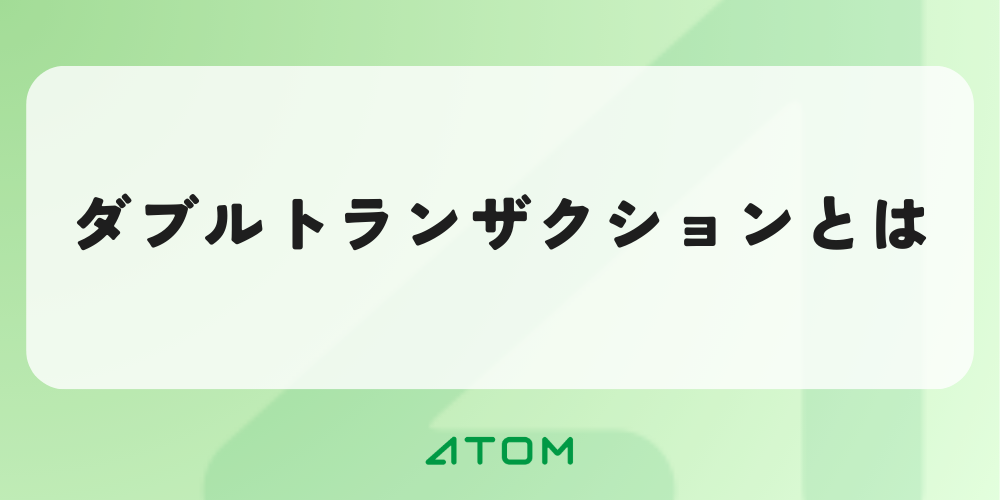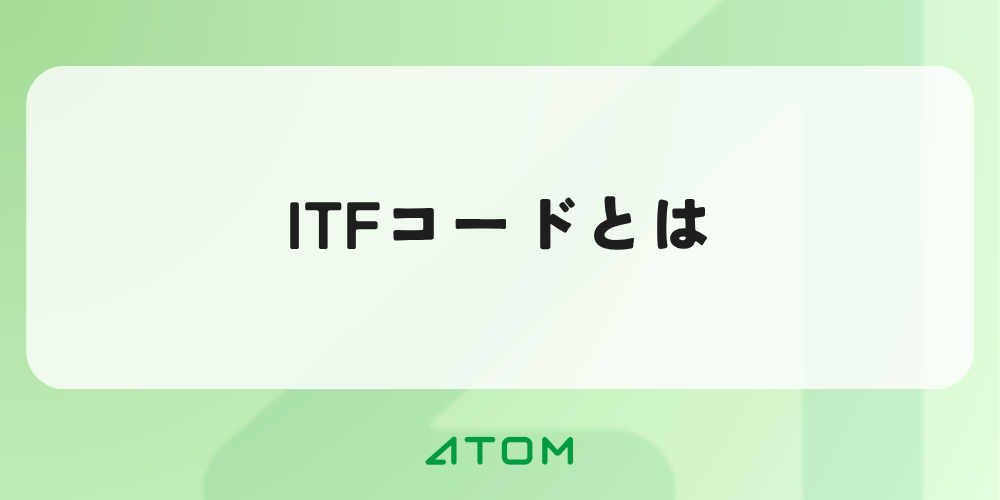お役立ちコラムCOLUMN
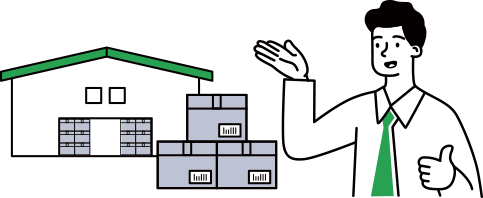
マルチピッキングとは?メリット・デメリットと他方式との違いを解説
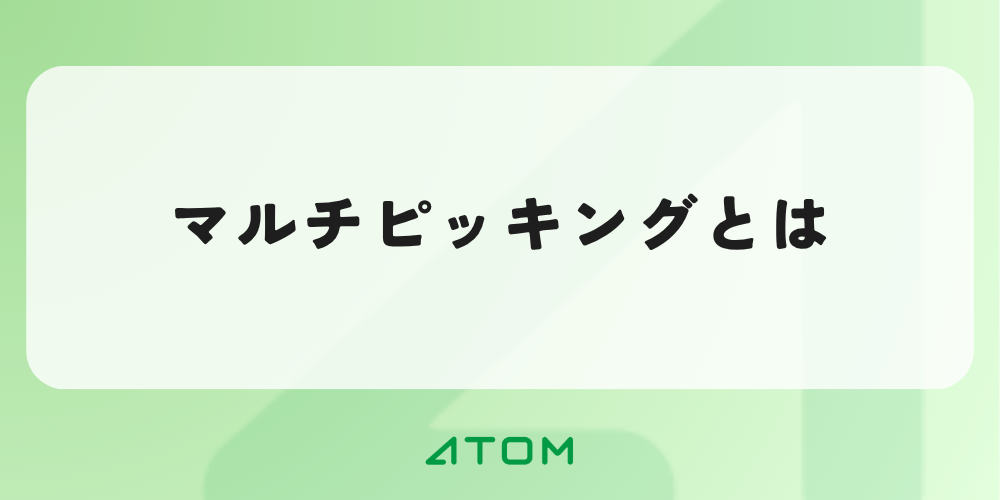
マルチピッキングは、複数のオーダーを同時に処理することでピッキング作業の効率を向上させる手法です。
この記事では、マルチピッキングの基本的な仕組みから、導入によるメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。
シングルピッキングやトータルピッキングといった他の方式との違いを比較し、さらにWMSや搬送ロボットなどの自動化システムを組み合わせることで、どのように生産性を高められるかについても詳しく紹介します。
マルチピッキングとは複数オーダーを同時に処理するピッキング方式

マルチピッキングとは、複数のオーダー(出荷指示)をまとめて一度にピッキングする方式です。
作業者は複数のオーダー用コンテナを積んだカートなどを使用し、倉庫内を一度巡回するだけで、各オーダーに必要な商品を同時に集品します。
1オーダーずつ商品をピッキングするシングルピッキングと比較して、同じ棚やエリアへの往復がなくなるため、作業者の移動距離を大幅に短縮できます。
この特性から、ECサイトの物流センターなど、多品種少量で出荷件数が多い現場での生産性向上に貢献する手法です。
マルチピッキングと他のピッキング方式の比較

ピッキング作業には、マルチピッキングの他にも複数の方式が存在します。
代表的なものとして、オーダーごとに作業を完結させるシングルピッキングや、商品単位で一括して集品し後から仕分けるトータルピッキングが挙げられます。
それぞれの方式は作業手順や適した現場の特性が異なり、メリット・デメリットも様々です。
自社が扱う商材の種類や量、倉庫の規模などを踏まえ、最適な方式を選択することが、物流全体の効率化において重要になります。
シングルピッキング:1オーダーずつ商品をピッキングする方法
シングルピッキングは、1つのオーダーリスト(ピッキングリスト)ごとに商品を集める、最も基本的な方式です。
作業者はリストを受け取ると、そのオーダーに必要な商品を全て集め終えるまで倉庫内を移動し、完了したら次のオーダーに取り掛かります。
作業内容が「リストを見て、指定の場所へ行き、商品を取る」という単純な流れのため、作業者が内容を理解しやすく、オーダーの取り違えといったミスが起こりにくいというメリットがあります。
しかし、オーダーごとに倉庫内を往復するため、商品の保管場所が広範囲に点在している場合、移動距離が長くなり非効率になりがちです。
小規模な倉庫や、1オーダーあたりの商品点数が多い場合に適しています。
トータルピッキング:商品単位でまとめてピッキングし後から仕分ける方法
トータルピッキングは、まず複数のオーダーに含まれる商品の種類(SKU)ごとに、その日の出荷に必要な総量をまとめてピッキングします。
その後、集めた商品を仕分けスペースに運び、オーダーごとに仕分ける(アソートする)という2段階の工程で作業を進める方式です。
商品ごとに一度でピッキングするため、倉庫内の移動距離が最も短くなり、ピッキング作業自体の生産性は非常に高くなります。
ただし、後工程としてオーダー別の仕分け作業が必須となり、そのための人員、時間、専用のスペースを確保しなければなりません。
出荷件数が非常に多く、特定の商品にオーダーが集中するような、少品種多量の商品を扱う大規模な物流センターで採用されることが多いです。
マルチピッキングシステム:マルチピッキングをさらに効率化させた方法
マルチピッキングとは複数オーダーを同時にピッキングする方式です。ピッキングと同時に仕分けを行い、また倉庫内の移動も1回で済むため、業務を効率化できます。
また、ピッキングカートにデジタル表示器や重量計を搭載し、どの商品をどの箱にいくつ入れるべきかを視覚的にガイドしたり、どの箱に入ったか重量でチェックすることで、複数オーダーを同時に処理する際に発生しがちな仕分けミスを防止します。
作業者の判断に依存する部分をシステムで補助することにより、経験の浅い作業者でも高い生産性と品質を維持できるため、教育コストの削減にもつながります。
マルチピッキングを導入する2つのメリット

マルチピッキングを導入することで、物流現場は作業効率とコストの両面で大きなメリットを享受できます。
特に、生産性の向上は直接的な効果として現れ、それが結果として人件費の削減にも結びつきます。
ここでは、マルチピッキングの2つのメリットを解説します。
作業者の移動距離が短縮され生産性が向上する
マルチピッキング最大のメリットは、作業者の移動距離を大幅に短縮できる点にあります。
ピッキング作業において、実際に商品を手に取る時間よりも、棚から棚へと歩いて移動する時間が大半を占めます。
シングルピッキングではオーダーごとに倉庫内を往復する必要がありますが、マルチピッキングでは一度の巡回で複数のオーダーを処理するため、同じエリアや通路を何度も通る無駄がなくなります。
特に、商品の種類が多く、保管場所が倉庫内に広く分散している場合、この効果は顕著に現れます。
移動時間という非生産的な時間が削減されることで、単位時間あたりに処理できるオーダー数が増加し、倉庫全体の生産性が飛躍的に向上します。
少ない人数で多くのオーダーに対応でき人件費を削減できる
生産性の向上は人件費の削減に直結します。
一人の作業者が単位時間あたりに処理できるオーダー数が増えるため、従来と同じ物量をより少ない人数で処理することが可能になります。
例えばこれまで5人の作業者が必要だった業務をマルチピッキングの導入によって4人や3人で対応できるようになる、といった省人化が実現します。
これにより人手不足が課題となっている物流業界において、作業人員の確保という負担を軽減できます。
また採用コストや労務費といった直接的な人件費を抑制することにもつながり、物流センターの収益性改善に大きく貢献します。
マルチピッキング導入時に注意したいデメリット

マルチピッキングは効率化に大きく貢献する一方で、デメリットも存在します。
複数オーダーを同時に扱うため仕分けミスが起こりやすい
マルチピッキングでは、作業者がピッキングした商品を、カート上にある複数のオーダー用コンテナへ正確に振り分ける作業(仕分け)が伴います。
この際、Aのオーダーの商品を誤ってBのオーダーの箱に入れてしまうといった、人的ミスが発生するリスクが高まります。
特に、類似した商品が異なるオーダーに含まれている場合や、作業に慣れていない段階ではミスが起こりがちです。
誤出荷は、顧客満足度の低下を招くだけでなく、返品対応や再発送にかかる余計なコストと手間を発生させます。
そのため、ハンディターミナルによるバーコード検品を徹底するなど、ミスを防止するための仕組み作りが極めて重要になります。
作業が複雑化するため作業者への教育が必要になる
1オーダーずつ完結させるシングルピッキングと比較して、マルチピッキングは複数のオーダー情報を同時に把握し、ピッキングと仕分けを並行して行うため、作業内容が複雑になります。
そのため、作業者がオペレーションに習熟するまでには一定のトレーニング期間が必要です。
特に、新人や経験の浅い作業者にとっては負担が大きく、導入初期にはかえって生産性が低下する可能性も考慮しなければなりません。
分かりやすい作業マニュアルの作成や、熟練作業者によるOJT(On-the-JobTraining)など、体系的な教育プログラムを準備する必要があります。
この教育にかかる時間やコストも、導入計画に含めておくべき要素です。
マルチピッキングの効率をさらに高める自動化システム

マルチピッキングは単体で導入するだけでも効果的ですが、各種自動化システムと連携させることで、その効率と精度をさらに向上させることが可能です。
テクノロジーを活用することで、デメリットとして挙げた作業の複雑さやミスの発生といった課題を根本的に解決し、生産性を最大化できます。
ここでは、WMS(倉庫管理システム)やボイスピッキングシステム、AGV・AMR(搬送ロボット)といった代表的なシステムを取り上げ、それぞれがマルチピッキングをどう支援するのかを解説します。
WMS(倉庫管理システム)で在庫や作業進捗を一元管理する
WMS(倉庫管理システム)は、マルチピッキングを効率的に運用する上で中核となるシステムです。
また、ハンディターミナルと連携して作業実績をリアルタイムに収集するため、進捗状況の可視化や、ピッキングミスの早期発見にも繋がり、倉庫全体の管理レベルを向上させます。
音声指示で作業するボイスピッキングシステムでミスを削減する
ボイスピッキングシステムは、作業者が装着したヘッドセットを通して、システムからの音声指示に従ってピッキングを行う仕組みです。
作業者は「ロケーションAへ移動」「商品Bを3個ピッキング」「2番のカートに入れる」といった具体的な指示を耳で聞きながら作業を進めます。
これにより、作業者はリストや端末画面を見る必要がなくなり、両手が自由に使える「ハンズフリー」と、視線を作業に集中できる「アイズフリー」が実現します。
その結果、作業スピードが向上すると同時に、複数オーダーの仕分け間違いといったヒューマンエラーを大幅に削減できるため、マルチピッキングの品質向上に大きく貢献します。
AGV・AMR(搬送ロボット)で作業者の移動負担を軽減する
自動化されている物流センターなどでは、AGV(無人搬送車)やAMR(自律走行搬送ロボット)でロボットが荷物の搬送を行います。
またGTP(Goods to Person)と呼ばれる商品棚を作業者の元まで自動で搬送する方式を活用することで作業者は定位置に待機し、ロボットが運んできた棚から指示された商品をピッキングして、手元のコンテナに入れるだけで作業を完了することもできます。
これにより、作業者の身体的負担を劇的に軽減し、生産性を最大限まで高めることが可能です。
特に大規模な物流センターにおいて、究極の省人化・効率化を実現するソリューションとして注目されています。
まとめ
マルチピッキングは、複数のオーダーを一度に処理することで作業者の移動距離を短縮し、生産性を向上させる有効なピッキング方式です。
これにより、少ない人数で多くの出荷に対応でき、人件費の削減にもつながります。
しかし、その一方で、作業が複雑化することによる仕分けミスのリスクや、作業者への教育コストといった注意点も存在します。
これらの課題を克服し、効率をさらに高めるためには、WMSによる最適な作業指示、ボイスピッキングによるミス防止、AGV・AMRによる移動の自動化といったシステムの活用が鍵となります。
自社の物量や商品の特性、倉庫の規模などを総合的に評価し、他のピッキング方式とも比較検討した上で、最適な手法を選択することが求められます。